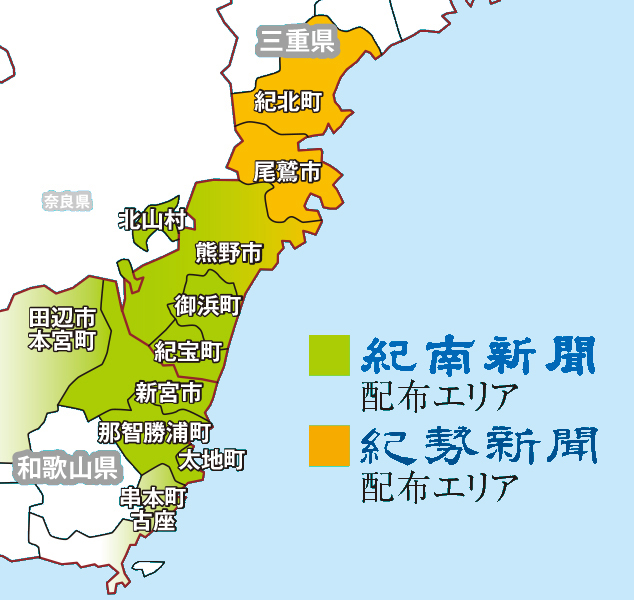取材はある種の演劇である。記者が演出家のように「事実」を切り取り、取材対象者が記事の登場人物となり、オーディエンス(読者)を意識しながら語ったり、動いたりする。取材を「する」「受ける」という双方の能動的な意識が少なからず働き、不自然な状況を作る。メディアは、報道が虚構を多少なりとも含むもの、あるいは虚構そのものであるという悲劇を免れられない。
例えば取材で、話し手はそれが新聞に掲載されることをわかって、言うこと・言わないことを選ぶ。時には、ある程度さみだれ式に話した後で「あとは良いようにまとめて」と言っていただく。記者はそれらを材料に「言いたいことはこれだろう」とまとめる。校正で直されたりもする。もはや誰の言葉か定かではないが、確かにその話者の発言として残る。ここに虚構が生まれる。
「事実」は、そういった虚構の上に立つ蜃気楼である。情報過多な現代にあって、読み手はその前提に立って何を信じるか選択する必要があるし、書き手は演劇性を自覚しながらも、出会ったさまざまな真実に誠心誠意言葉を尽くさねばならない。
【稜】
 LINE
LINE