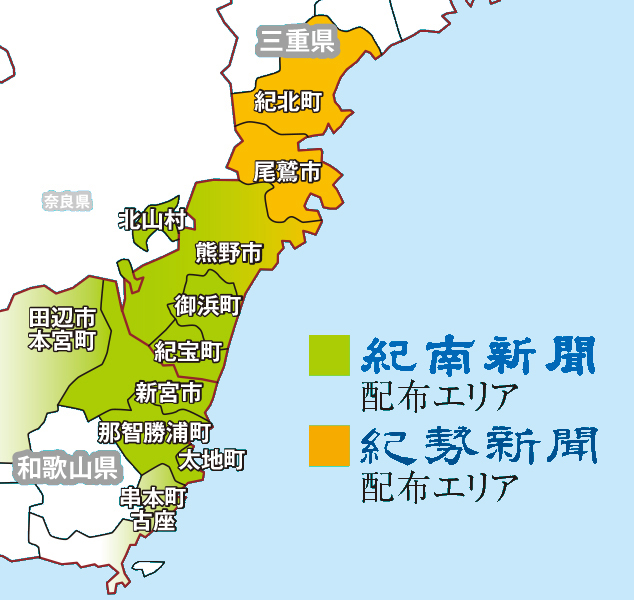ファンタジー作家で文化人類学者の上橋菜穂子さんは「この世界は全て想像でできている」と話した。その場ではこの言及は深堀りされなかったが、例えば「お金には価値がある」と全員が信じているからお金が貨幣として運用できるみたいな、それぞれの想像力がこの世界の実体となって浮き上がる、というようなことだろうか。
文化でもそうだ。当地方では「私たち」の意味で「わがら」と言うが、これを地元の人だけで使っている分には意味の通った言葉として信頼して使える。しかし観光客や移住者など“外”の人と話していて「その言葉は何?」と指摘された瞬間、当たり前に通用していた言葉が、意味の通り得ないものだったのだという危機にさらされる。
異なる世界が混じり合うことで初めて、それまでの通念が単なる共通の想像でしかなかったことに気が付く。人は想像によって自分の世界を作り、その周辺同士が触れ合うことで、雨粒が水たまりに当たって波紋がいくつも刺激し合うように、新しい世界が運動する。ならばその触れ合いが、願わくば対立ではなく調和であればいいなと思う。
【稜】
 LINE
LINE