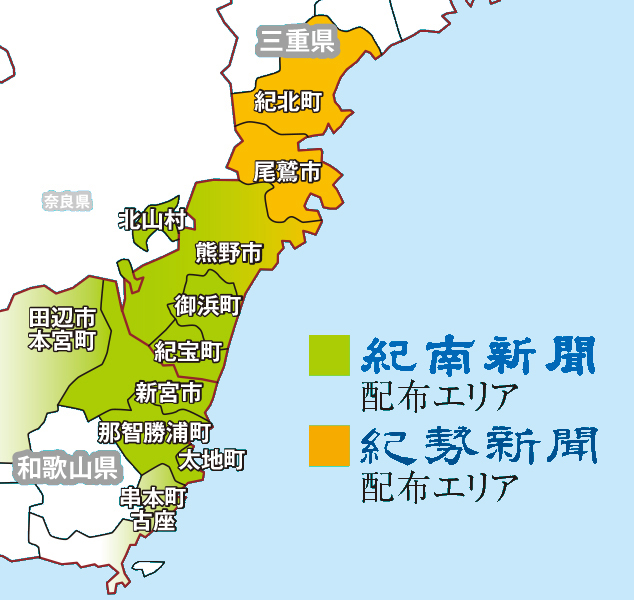紀北町の防災講演会で登壇した自衛官は「能登半島と三重は似ている」と指摘する。地理的に孤立集落が生まれやすく、過疎が進む中での復興の担い手不足も問題となる。
東日本大震災と能登半島地震から、南海トラフ地震に対して学ぶべきことは多い。内閣府の東日本大震災後の報告書によると、津波浸水面積と人口と事業所の減少は相関関係がみられ、海とともに生きてきたまちとしては死活問題に直面する。地域経済は変容し、地域によっては生活再建にもばらつきが出ている。
能登半島地震は元日に発生した点も特徴だが、自治会や町内会レベルで住民の状況を把握できたのは大きかったという。
先の昭和東南海地震後はまちが新しくなり、人も増えていった。南海トラフは100~150年間隔で地震を繰り返しているが、人口が減少する中での災害復興という新しい局面を迎える。人口減少の中では、南海トラフ地震は集落消滅の引鉄になりかねない。自助、共助、公助の全てで、しっかりとした事前対策が求められる。
(R)
 LINE
LINE