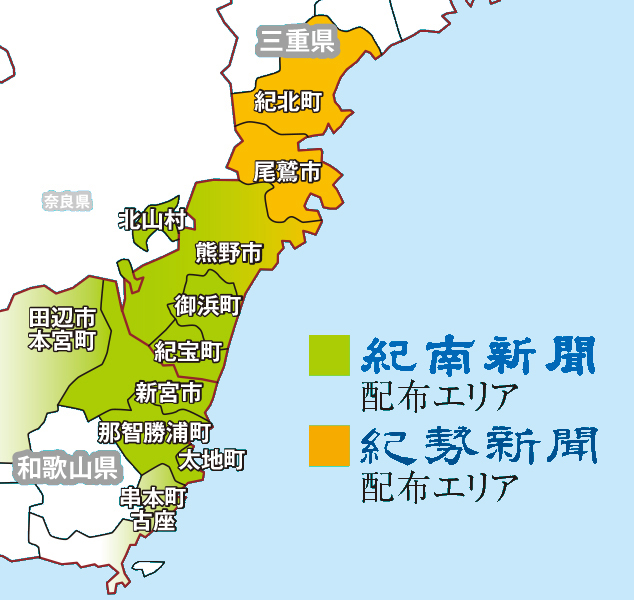山が真っ赤に染まった日。一夜明けると、もうあれが現実だったような気がしない。ただ服に染みついた煙のにおいが、お燈祭りの中にいたことを教えてくれる。
古代から営々と続く流れの中に今があると体感する。過去も未来も切り離すことはできず、連続している。結果があれば原因があるように。例えば今の自分は、へんな微生物みたいな時代から、先祖が代々続いて、一度も途切れなかったから生まれてきたのだ。天文学的な確率が生んだそのつながりは、誰も否定できない。
小さな1つの火種が大きな炎になり、それが次第にいくつも分かれていき、やがては暗闇というカオスを照らす。宇宙のはじまりや生命の起源、お母さんのお腹の中も、あるいはこんな風だったのだろうか。
祭りの最中、子どもの泣き声が聞こえた。父親らしき人が「お前男や。立派だぞ」としきりにいさめる。祈りも祭りもお燈の火も、涙をこらえる子どもの顔も、そのどれもが決意に似ている。祈願とは、神様に頼ってお願いすることなのだろうか。もしかすると、自分はこうあるぞと、固く誓うことなのだろうか。
【稜】
 LINE
LINE