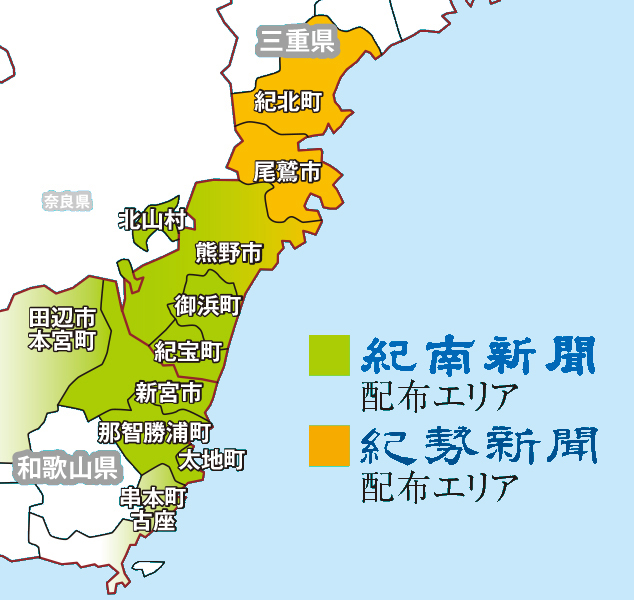「わっしょい、わっしょい」。子どもから大人まで、男性も女性も、威勢の良い掛け声とともに神輿が田辺市本宮町の中心地を練り歩いた。今月15日、熊野本宮大社例大祭「本宮祭」の最終日に行われた「渡御祭」(とぎょさい)は、参列者と見物客合わせ約800人が集まる盛況ぶり。祭りによって地域の一体感が示された光景だった。
祭りといえば、地域の安寧を願ったり、五穀豊穣(ほうじょう)に感謝したりと、地域密着の行事だ。祭りの報道ではよく"お祭りムード一色"と表現されるが、本宮祭はまさにその通りではないか。老若男女問わず、さまざまな形で祭りに携わっているのが特徴で、地元の小中学生は舞奉納や神輿の担ぎ手として毎年参加している。地域の歴史・文化を肌で感じることができる貴重な機会として学校側も積極的に協力。子どものころの経験が、将来的に地域の祭り継承への思いを強くさせ、うまくバトンが渡されている。縁起物の菊の造花「挑花」は同大社の敬神婦人会が奉製。今年もメンバーそれぞれが健康や多幸さらに世界平和への願いを込めて作った。昨年ごろからは外国人の参列者も目立っている。東京大学の留学生や田辺市熊野ツーリズムビューローのツアー参加者など今年も15人以上が神輿を担いだ。参列者同士の交流が生まれるなど、国際色豊かで多様性にあふれる今の社会にマッチした流れにもなっている。
本宮のまちの規模的に一体感が生まれやすいということはあるかもしれないが、ほかの地域でも一つのモデルにすることはできないか。特に子どもたちの参加については、教育委員会と学校の理解・協力が不可欠。新宮市内の小中学校でもふるさと学習に取り組んでいるが、実際の祭りにどのような形でも参画できれば、机上の学習では得られない体験ができる。近くにある"生きた教材"をぜひ活用してほしい。
祭りで生まれた地域の一体感は、日常生活に生き、ひいては防災の取り組みでも有効になる。少子高齢化が進む中、南海トラフ地震への備えでは、まず自助そして共助が基本になる。近所づきあいが希薄になる今だからこそ、祭りなど地域の行事を通して顔見知りになり、交流が続けることが大切ではないか。
 LINE
LINE