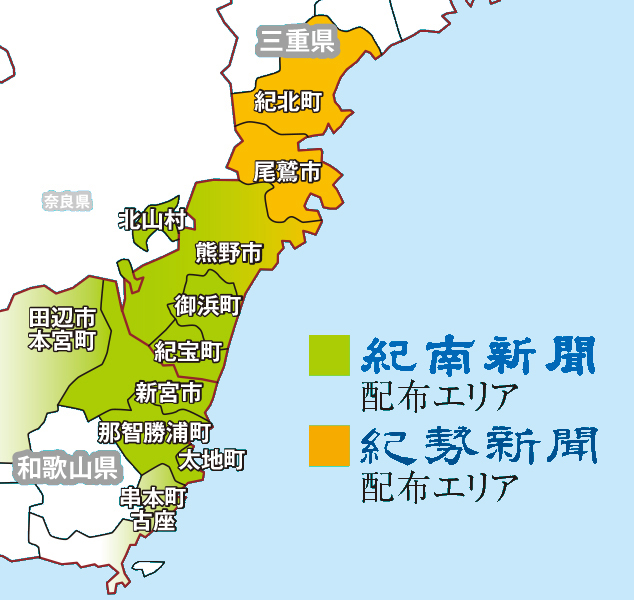梅雨に入り、これから大雨や台風の時期。和歌山・三重・奈良の3県で死者・行方不明者88人を出した紀伊半島大水害(2011年9月)以降、甚大な被害を伴う水害が毎年のように全国各地で発生しており、どこにいても被災する可能性はある。6月は土砂災害月間でもあり、この機会に「自分事」として捉え、備えを点検することが大切。
災害時の基本原則として「自助・共助・公助」がよく言われる。まずは自分の命は自分で守る。その観点からも、行政頼みではなく、各家庭での備蓄も進めなければならない。風水害や地震などの自然災害では、水道・電気・ガスなどのライフラインが寸断されることが想定される。たとえ自宅が無事で避難せずとも、早期の復旧は難しく、スーパーなどの店舗が機能しているかどうかも分からない。発災直後は行政の支援が入らないことを想定し、飲料水を「家族人数×3リットル×3日分」確保してほしい。また、ポリタンクや浴槽に水を備えておけば、生活用水として使用することができる。
避難所や避難経路、ハザードマップで土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの情報をあらかじめ家族で確認・共有しておくことも求められる。
備えと併せて大切なのが情報入手。気象予測の技術の進歩で、台風を含む大雨災害は、事前に高い確率でどこにどれだけの雨が降るか予想できる。人的被害を避けるには「早めの避難」が大切と言われるが、事前に気象情報を把握することで、明るいうち、または被害が出る前に避難することが可能。気象庁のホームページの「キキクル」は、土砂災害、浸水、河川の洪水の危険度分布をリアルタイムに、黄「注意」、赤「警戒」、紫「危険」、黒「災害切迫」と色分けで表示している。
一方、行政には平時から、住民の命を守る備えに万全を期してほしい。紀伊半島大水害から今年で14年。自治体の中には大水害を経験していない職員の割合が高くなってきたところもある。災害時の基本は自助・共助・公助の順だが、住民への啓発や避難所準備や備蓄などの面で各自治体は責任を持って取り組まなければならない。職員一人一人が当時の教訓を振り返る機会を設けてはどうか。開会中の6月議会で、災害の備えについても議論してもらいたい。
 LINE
LINE