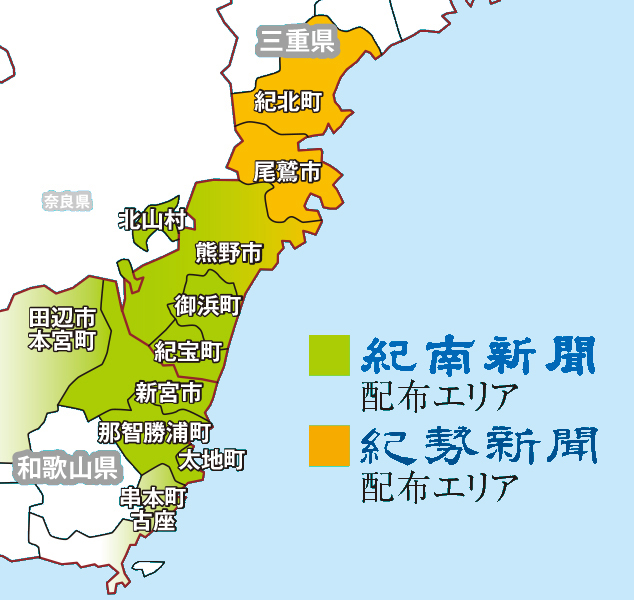尾鷲市向井、熊野古道センターで14日、尾鷲林業の歴史について学ぶ講演会が開かれた。濵中林業の濵中良平代表が古文書を紐解き、紀州藩や住民に利益をもたらした林業の成り立ちを説明した。
同センターで開催中の企画展「尾鷲林業が歩んだ400年」の付属事業で、「江戸時代の木と米と税金」を演題とした。賀田町の濵中林業は元禄13(1700)年創業で、9代目当主の濵中代表は尾鷲古文書の会の会長を務めており、歴史と林業に深い知見を持っている。
濵中代表は紀州藩が寛永13(1636)年に公布した奥熊野山林定書に着目。奥熊野(長島、相賀、尾鷲、木本、入鹿、北山、本宮)の山林では、8尺(およそ2.5メートル)以上の杉・ヒノキ・松・クスノキ・ケヤキ・カヤの〝紀州六木〟の伐採を禁止したが、それ以外は藩が関与しなかったため、浦村では炭焼きが盛んとなったと説明した。
伐採後の山に勝手に杉が植林されていき、これが村の管理している山林に植えた木を個人が所有できる〝植出し権〟につながり、天然の木を切る林業から、木を育てる林業へ転換していった。
民間が育てた木に、紀州藩は日本で初めて材木の流通に2割、杉とヒノキには1割の税を課すことになった。課税単位は米と同じく石・斗・升・合といった体積で、昭和40年まで続いた。
江戸幕府の開祖・徳川家康の10男の頼宣が紀州を領有した経緯について、「55万石のはずが37万石しかなく、紀伊に加えて、伊勢田丸や松坂、鈴鹿白子を加増された」と説明し、自身が書いた絵を提示。絵は荷坂峠から山しかない領地が不本意な頼宣に、付家老の安藤帯刀(直次)が「いつかこの山が役に立つときが来る」と言い含めている。
 LINE
LINE