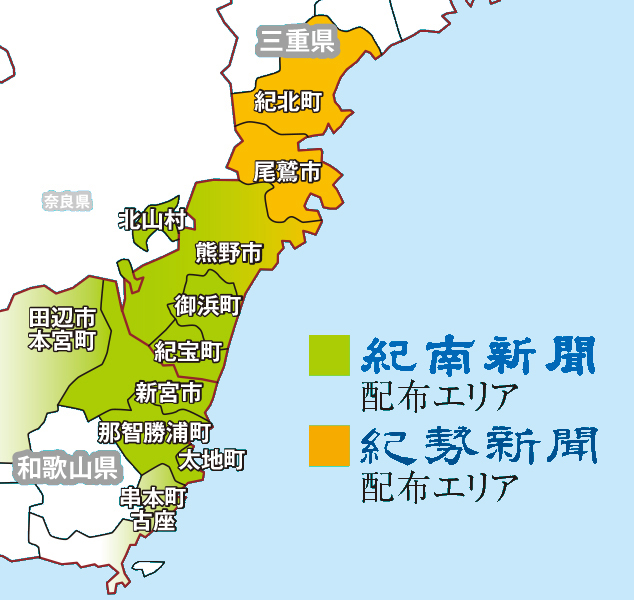熊野古道協働会議がこのほど、尾鷲市向井の三重県立熊野古道センターで開かれた。6人の世話人のほか、東紀州内外のルートの保全団体や観光関係者、県や市町の観光、文化財担当職員ら20人余りが参加し、熊野古道活用プラン(仮)の中間案などについて意見交換した。
熊野古道アクションプログラム3追記編に関する進行管理状況の報告の後、活用プランの案について事務局の県東紀州振興課が説明した。
同プランは、熊野古道伊勢路を効果的に活用した地域経済の振興、観光のための基盤整備など、県として取り組みが必要な課題について、昨年の世界遺産登録20周年を契機にアクションプログラムで定めた伊勢路の目指す姿である「『歩き旅』を象徴的なイメージとしながら、さまざまな目的で人々が伊勢路を訪れ、それが地域の活力になっている」の実現に向けた取り組みを明らかにするため策定する。期間は令和7年度から11年度の5年間。
主な内容
- 観光インフラ整備
多言語対応の案内標識の整備、トイレの洋式化、JR特急と連動する2次交通の利便性向上、自家用車でのアクセス方法の検討、地域の観光施設等への誘客促進、インバウンド向けの高付加価値宿泊施設の誘致
- 魅力の発信
(伊勢と熊野の)二大聖地を結ぶ絶景の道としての魅力発信やプロモーション、峠ごとの魅力や周遊コースなどの情報発信
- 和歌山県、奈良県と連携した効果的なプロモーション・案内機能の強化
- 熊野古道センターの常設展示のリニューアルによる魅力発信や多言語化・DX化による集客交流の強化
- 保全
保全活動にかかる支援策の検討、サポーターズクラブの参加促進、企業や団体・外部ボランティアの受け入れによる担い手確保、ふるさと納税など新たな財源確保策の検討、次世代継承のための啓発活動や体験機会の充実
保全活動強化へ 仕組みづくりを
情報発信について、絵地図作家の植野めぐみさんはSNSでの情報発信について「1万回見られた動画があっても、次の動画を見ればその内容は忘れられてしまう」と語り、閲覧数だけでは効果が測れないと話した。
大杉谷自然学校の大西かおり代表は、未登録部分など北の方(大台町~大紀町)の峠に来てもらう方策はどうか」と尋ね、「西国巡礼との関係を前に出すのがいい」と提案した。また、保全については「保存会員を増やす取り組みを」と話した。
世話人で県職員の佐波斉さんは「登録された部分だけで、とは考えていない。大台、多気、玉城地区も含めてどう保全・活用していくかということ」と県の見解を説明し、「保存会や市町の人と十分に話をしたい。伊勢路の応援団として、多くの人に来てもらえるようにしたい」と回答した。
熊野市の逢神坂峠の保全に携わっている西山光雄さんはサポーターズクラブの会員による保全活動に関連し「年1回来てもらっているが、ちゃんとやろうと思ったら年間3~4回必要。受け入れは、各峠の世話人が準備していてけっこう手間はかかる」と述べ、受け入れのための仕組みづくりが必要で、県の支援を呼び掛けた。
代表世話人の速水亨さんは「素人が作業して成果の出来る場所を探して、何人をいつ受け入れるかなど大変」と受け入れ側に気配りを示し「効果的に保全活動に来てもらうためのパッケージが必要。単発では長期的に取り組んでいければ効果が出てくるのでは」と話した。
利活用には、道が歩ける状態で残っていることが前提だが、保全会員は高齢化し人数も減っていて担い手不足となっている。「10年後には道が通れなくなっているのでは」との危機感も示された。
 LINE
LINE