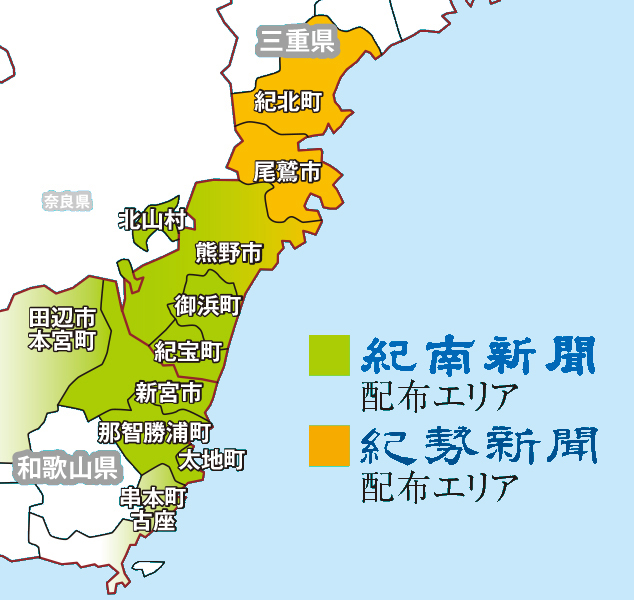新宮市の阿須賀神社境内にある市立歴史民俗資料館で20日(日)まで、企画展「阿須賀神社の御正体~重要文化財の保存修理と未来への継承~」が開催されている。国の重要文化財に指定された「阿須賀神社境内(蓬莱山)出土品」について、その内容や価値、市が2022年度~24年度に行った保存修理の作業内容・工程などを実物とともに紹介している。
「御正体(みしょうたい)」とは、鏡や鏡板(円形の銅板)に神仏の像などを表したもので、平面的な「鏡像(きょうぞう)」と、そこから発展した立体的な「懸仏(かけぼとけ)」に分かれる。弥生時代から続く鏡を神聖視する伝統に基づき、平安時代から中世を通して大量に生産されるようになった。
「阿須賀神社境内(蓬莱山)出土品」は1960年に発見され、翌年に発掘された。平安末期から室町ごろまでの350点が出土し、御正体は190点弱が確認されている。日本での鏡像から御正体への変遷を示す一括資料で、神仏習合により隆盛を極めた熊野信仰のあり方を示す学術的価値の高いものとして、2019年7月に国の重要文化財に指定された。
企画展では、御正体を中心とした出土品の実物を展示。鎌倉時代のものが多く、風合いある品がいくつも並ぶ姿から、古い時代の熊野信仰の盛り上がりを感じさせる。
御正体の中でも、鏡板が残るもので最大である大威徳明王(だいいとくみょうおう)の懸仏は、銅板の直径が60センチ。尊像は頭と体、第1手、水牛の体を一度に鋳造し、脇手はそれぞれ鋳造して接合してある。牙をむき憤怒の表情だが、どこか愛嬌を感じさせる。
なお、大威徳明王は阿須賀神社の祭神の本地仏(ほんじぶつ、本地垂迹〈すいじゃく〉説に基づく、神の本体とされる仏・菩薩のこと)で、境内で出土した御正体の多数を占める。その他は熊野三山の祭神の本地仏である薬師如来や阿弥陀如来などの尊像がある。
市では、出土品の劣化が激しかったことから、貴重な文化財を適切に保存管理・展示活用し、安定した状態で未来へと継承するため、22年度から保存修理を行っている。今回は24年度にかけて保存修理を行った完成品19点とともに、作業内容や工程について写真も交えて紹介している。
展示では「これらを通じて、熊野信仰の歴史文化や文化財の保存継承の理解につなげていただければ幸いです」と伝えている。
 LINE
LINE