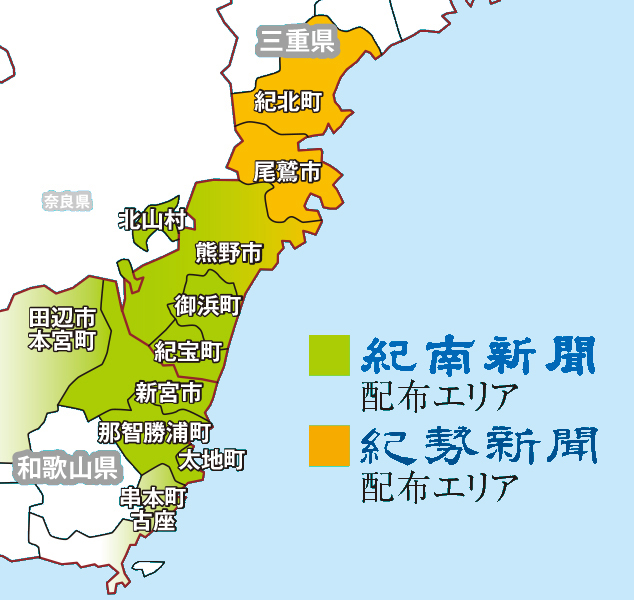この記事は購読者限定です。太平洋新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
新宮市
-
佐藤春夫の資料寄贈 太宰や芥川の書簡など1万3千点 記念館で展示予定佐藤春夫の資料寄贈 太宰や芥川の書簡など1万3千点 記念館で展示予定
-
1位に池上さんの作品 全日写連新宮支部 1月例会の結果1位に池上さんの作品 全日写連新宮支部 1月例会の結果
-
幸福の「節分吉兆」 大小1200本を奉製 熊野速玉大社幸福の「節分吉兆」 大小1200本を奉製 熊野速玉大社
-
「有事には駆け付けます」 陸上自衛隊第37普通科連隊 新宮で装備品や車両展示「有事には駆け付けます」 陸上自衛隊第37普通科連隊 新宮で装備品や車両展示
-
ロックで寒さ吹き飛ばす 新宮市民音楽祭 盛況ロックで寒さ吹き飛ばす 新宮市民音楽祭 盛況
-
新宮高校が「金賞」 県アンサンブルコンテスト 吹奏楽 21年ぶり快挙新宮高校が「金賞」 県アンサンブルコンテスト 吹奏楽 21年ぶり快挙
-
「餅ほり」で厄ばらい 同級生有志の会 無病息災を祈願「餅ほり」で厄ばらい 同級生有志の会 無病息災を祈願
-
北方領土の日 各地で街頭啓発北方領土の日 各地で街頭啓発
-
「希望に満ちた未来に」 近大新宮高"最も早い"卒業式 98人が旅立ち「希望に満ちた未来に」 近大新宮高"最も早い"卒業式 98人が旅立ち
-
新宮「学彩探究科」は9人 県立高校の特色化選抜出願状況新宮「学彩探究科」は9人 県立高校の特色化選抜出願状況
-
災害に備え知識学ぶ 新翔高校1年生・防災スクール災害に備え知識学ぶ 新翔高校1年生・防災スクール
-
「なぎの湯」時間変更 2月6日 「お燈祭り」開催で「なぎの湯」時間変更 2月6日 「お燈祭り」開催で
-
AI活用でどう変わる 新宮商工会議所青年部が例会AI活用でどう変わる 新宮商工会議所青年部が例会
-
水道事業所の公示入札結果水道事業所の公示入札結果
-
地域に生き続けた 「ドクトル大石」 大逆事件犠牲者・大石誠之助地域に生き続けた 「ドクトル大石」 大逆事件犠牲者・大石誠之助
-
能登へ思い届け 土のう袋に防災アート 放課後アカデミー能登へ思い届け 土のう袋に防災アート 放課後アカデミー
最新記事
-
[ 新宮市 ] 佐藤春夫の資料寄贈 太宰や芥川の書簡など1万3千点 記念館で展示予定佐藤春夫の資料寄贈 太宰や芥川の書簡など1万3千点 記念館で展示予定
-
[ 紀北町 ] 商品券配布で消費下支え 紀北町議会 補正予算など可決商品券配布で消費下支え 紀北町議会 補正予算など可決
-
[ 尾鷲市 ] 入学祝い金など審議 尾鷲市、30日に臨時議会入学祝い金など審議 尾鷲市、30日に臨時議会
-
[ 紀北町 ] 楽しんで福祉学ぶ スクエアボッチャを体験楽しんで福祉学ぶ スクエアボッチャを体験
-
[ 選挙 ] 三重4区は3氏の戦い 政権枠組みや物価高対策争点 消費税減税掲げる党多く三重4区は3氏の戦い 政権枠組みや物価高対策争点 消費税減税掲げる党多く
-
[ 選挙 ] 和歌山2区は2人の争い 衆院選公示和歌山2区は2人の争い 衆院選公示
-
[ 那智勝浦町 ] 1人1万8千円の商品券 臨時議会へ補正予算 那智勝浦町1人1万8千円の商品券 臨時議会へ補正予算 那智勝浦町
-
[ 紀宝町 ] 向井氏に当選証書 紀宝町選管 初登庁は2月5日向井氏に当選証書 紀宝町選管 初登庁は2月5日
-
[ 紀北町 ] やったこと積み重なる 過去振り返り防災をつなげる 耐震化で町のリスク低下やったこと積み重なる 過去振り返り防災をつなげる 耐震化で町のリスク低下
-
[ 尾鷲市 ] 有機農業振興を支援 東京の会社が寄付と協力申し出有機農業振興を支援 東京の会社が寄付と協力申し出
-
[ 三重県 ] 12月末で96.2% 高校生の就職内定率12月末で96.2% 高校生の就職内定率
-
[ 尾鷲市 ] ツキノワグマか 九鬼町の国道311号ツキノワグマか 九鬼町の国道311号
-
[ 那智勝浦町 ] 那智山で防火訓練 文化財を後世に守り伝える那智山で防火訓練 文化財を後世に守り伝える
-
[ 紀宝町 ] 災害時の危険箇所点検 相野谷小中 合同で防災学習災害時の危険箇所点検 相野谷小中 合同で防災学習
-
[ 和歌山県 ] オープンキャンパス 和歌山県農林大学校農学部オープンキャンパス 和歌山県農林大学校農学部
-
[ 紀宝町 ] 除災招福や身体健全願う 神内の延命地蔵で例祭除災招福や身体健全願う 神内の延命地蔵で例祭
-
[ 新宮市 ] 1位に池上さんの作品 全日写連新宮支部 1月例会の結果1位に池上さんの作品 全日写連新宮支部 1月例会の結果
-
[ 和歌山県 ] 和歌山県の海域での海難 船舶事故は減少 人身事故は増加 昨年中和歌山県の海域での海難 船舶事故は減少 人身事故は増加 昨年中
-
[ スポーツ「躍動」 ] 那智勝浦ゴルフ 月例杯の結果那智勝浦ゴルフ 月例杯の結果
-
[ 紀南紗 ] 紀南抄「庶民の味覚に戻って」紀南抄「庶民の味覚に戻って」
 LINE
LINE