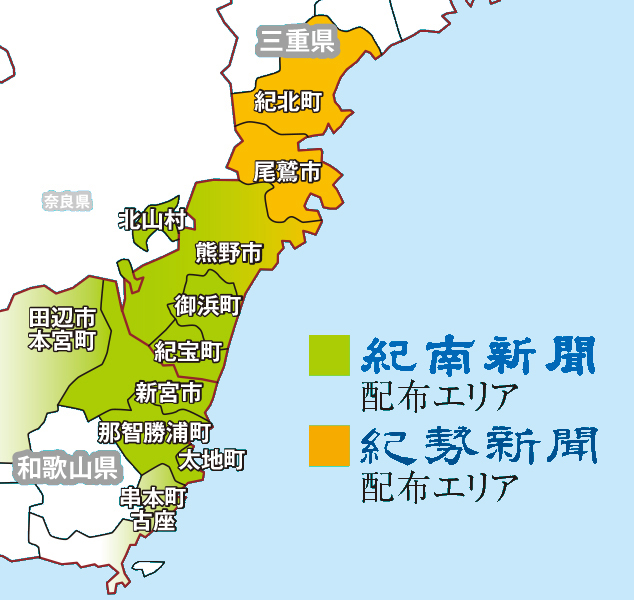この記事は購読者限定です。太平洋新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
新宮市
-
今後の学校再編は 新宮市総合教育会議今後の学校再編は 新宮市総合教育会議
-
災害時の知識身に付ける 近大新宮高校で防災スクール災害時の知識身に付ける 近大新宮高校で防災スクール
-
新理事長に中納さん 新宮青年会議所が総会新理事長に中納さん 新宮青年会議所が総会
-
お燈祭り 御神火授ける役割全う 大松明へ祈願文書き入れお燈祭り 御神火授ける役割全う 大松明へ祈願文書き入れ
-
建設産業の今後を展望 見坂参院議員の国政報告会建設産業の今後を展望 見坂参院議員の国政報告会
-
「命は戻らない」 大水害被災者が講演 神倉地区防災イベント「命は戻らない」 大水害被災者が講演 神倉地区防災イベント
-
餅つき体験 楽しむ 中央児童館の子どもたち餅つき体験 楽しむ 中央児童館の子どもたち
-
新宮駅は市の玄関 花壇に苗を植える新宮駅は市の玄関 花壇に苗を植える
-
高校ラグビー東西対抗戦で活躍 松畑さんが市長表敬高校ラグビー東西対抗戦で活躍 松畑さんが市長表敬
-
「創作の楽しさ知って」 木版画家がワークショップ「創作の楽しさ知って」 木版画家がワークショップ
-
新翔2年中さんが最優秀 県立図書館のPOPコンクール新翔2年中さんが最優秀 県立図書館のPOPコンクール
-
訓練成果や課題を共有 災害対策本部報告会 新宮市訓練成果や課題を共有 災害対策本部報告会 新宮市
-
佐野区に3連覇を報告 光洋地区綱引き大会佐野区に3連覇を報告 光洋地区綱引き大会
-
救命講習に参加を 新宮市消防署 3月に開催救命講習に参加を 新宮市消防署 3月に開催
-
県大会で優勝、全国へ 近大新宮高の榎本さん 「ビブリオバトル」県大会で優勝、全国へ 近大新宮高の榎本さん 「ビブリオバトル」
-
筋力アップ目指す 楽しみながら健康体操筋力アップ目指す 楽しみながら健康体操
最新記事
-
[ 那智勝浦町 ] 邪気払い福招きで春へ 那智山で節分行事 無病息災や家内安全願い邪気払い福招きで春へ 那智山で節分行事 無病息災や家内安全願い
-
[ 新宮市 ] 今後の学校再編は 新宮市総合教育会議今後の学校再編は 新宮市総合教育会議
-
[ 尾鷲市 ] 消費喚起策を積極的に 製材工場「待つだけでなく」 商工会議所が尾鷲市に要望消費喚起策を積極的に 製材工場「待つだけでなく」 商工会議所が尾鷲市に要望
-
[ 尾鷲市 ] 威勢よくヤーヤの練り 「チョーサじゃ」の声響く威勢よくヤーヤの練り 「チョーサじゃ」の声響く
-
[ 尾鷲市 ] 献血キャンペーン 2月4 尾鷲市役所前献血キャンペーン 2月4 尾鷲市役所前
-
[ 紀宝町 ] 皆の力結集で夢実現 紀宝町の西田町長 町政担った5期20年振り返る皆の力結集で夢実現 紀宝町の西田町長 町政担った5期20年振り返る
-
[ 選挙 ] 衆院選和歌山2区 畑野氏 「国民の暮らし第一へ」 新宮市などで街頭演説衆院選和歌山2区 畑野氏 「国民の暮らし第一へ」 新宮市などで街頭演説
-
[ 新宮市 ] 災害時の知識身に付ける 近大新宮高校で防災スクール災害時の知識身に付ける 近大新宮高校で防災スクール
-
[ 北山村 ] 送迎で投票支援 北山村、衆院選でも対応送迎で投票支援 北山村、衆院選でも対応
-
[ 事件・事故 ] 電子マネー送金 恐喝で男逮捕電子マネー送金 恐喝で男逮捕
-
[ 尾鷲市 ] 曽根石の魅力に迫る 文化財調査の結果など伝える曽根石の魅力に迫る 文化財調査の結果など伝える
-
[ 尾鷲市 ] 英数の試験と面接 尾鷲高校でも前期入試英数の試験と面接 尾鷲高校でも前期入試
-
[ 尾鷲市 ] 過去最高目指して 美し国駅伝 尾鷲チーム壮行会過去最高目指して 美し国駅伝 尾鷲チーム壮行会
-
[ 三重県 ] 1月の雨「0ミリ」 アメダス紀伊長島1月の雨「0ミリ」 アメダス紀伊長島
-
[ 熊野市 ] 「お綱かけ」で豊穣祈願 花の窟神社で春季例大祭「お綱かけ」で豊穣祈願 花の窟神社で春季例大祭
-
[ 熊野市 ] 災害時の拠点運営に備え 紀南地域活性化局が研修災害時の拠点運営に備え 紀南地域活性化局が研修
-
[ 新宮市 ] 新理事長に中納さん 新宮青年会議所が総会新理事長に中納さん 新宮青年会議所が総会
-
[ 三重県 ] 中井美結さん知事賞 県海の子作品展 本紙関係3人入賞中井美結さん知事賞 県海の子作品展 本紙関係3人入賞
-
[ 連載・特集 ] 2月6日斎行 神倉神社例大祭「お燈祭り」2月6日斎行 神倉神社例大祭「お燈祭り」
-
[ 紀南紗 ] 紀南抄「雪国の生活は大変」紀南抄「雪国の生活は大変」
 LINE
LINE