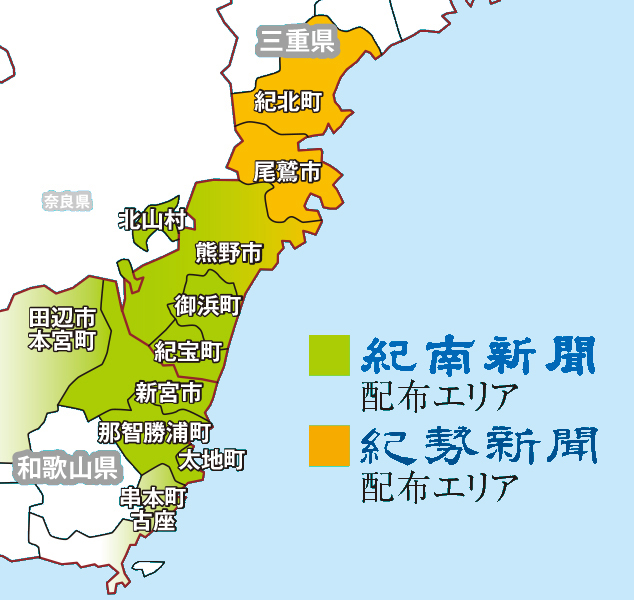「桂文三(かつら・ぶんざ)の新春寄席」の取材のため、新宮市木ノ川にある宝珠寺にお邪魔した。落語を生で鑑賞するのは初体験。尊敬する先輩が落語好きだったため、故・桂米朝師匠の「天狗さし」を視聴したこともある。が…オチで全く笑えず断念。以来、落語は頭のいい人しか理解できない笑いであると決めつけ、縁遠いものとなっていた。
高座に上がった文三さんのマクラ(本題に入る前のトーク)は軽快で存分に楽しめた。また、本題も、その秀でた話芸に魅了された。文三さん曰く「落語は辛抱の芸。漫才はテンポが速く、随所に笑いを誘う。落語と漫才は似て非なるもの」と解説していた。
噺(はなし)の最後に「オチ」がつくのが落語の特徴。ほかの伝統芸能と違い、落語は身振りと手振りのみで噺を進め、一人何役も演じる。衣装や舞台装置など極力使わず、演者の技巧と聴き手の想像力で噺の世界が広がっていく、とてもシンプルで身近な芸能。
寄席には、普通に生活を営んでいる人たちが、みんなで一緒に笑っていた。「非日常」ではなく、「日常」の中の笑いが心に染みた。
【茂】
 LINE
LINE